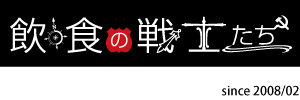
第432回 銀座小十 銀座奥田 店主 奥田 透氏
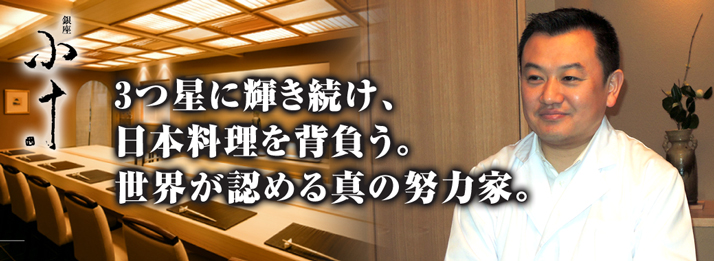
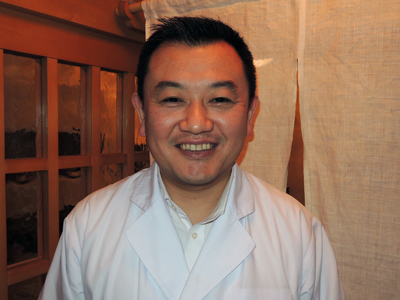
| 銀座小十 銀座奥田 店主 奥田 透氏 | |
| 生年月日 | 1969年10月18日 |
| プロフィール | 静岡県生まれ。高校を卒業し、静岡市内の割烹旅館「喜久屋」に就職。料理人人生がスタートする。「喜久屋」を皮切りに、京都の老舗料亭に勤務した後、「青柳」で小山裕久氏に師事。この時、生涯の親友であり、ライバルという「龍吟」の山本征冶氏に出会っている。「銀座小十」オープンは2003年。「ミシュラン東京」で三つ星を獲得。2013年9月にはパリにて「OKUDAパリ」をオープンさせた。著書には「世界でいちばん小さな三つ星料理店」も。 |
| 主な業態 | 「銀座小十」「銀座奥田」「鮨かくとう」 |
| 企業HP | http://www.kojyu.jp/ |
野球少年時代の話。
駿河湾の海岸線は、御前崎を西の突端に、西から辿れば左にカーブを描きつつ、大きく反転しながら、静岡、神奈川、東京、千葉と、4つの県を舐める様にしてから房総半島の突端に繋がっていく。
奥田が生まれた静岡市駿河区下川原は、この駿河湾に面した小さな町で、有名な漁港「焼津港」を少し北に進んだ所にある。付近には安倍川という大きな川が流れ、こちらは少年、奥田の格好の遊び場だった。
奥田は3人兄弟の長男で、妹と弟がいる。父は郵便局員。普段は温厚な性格だが、話が野球の事となると別人になったそうだ。その父の影響もあったのだろう。奥田は、小学校に入学すると同時にソフトボールを始めた。
「毎日、暗くなるまでボールを追いかけていた」と奥田。「学校の行き帰りの時間も無駄にすまいと、爪先立ちで通った」とも言っている。そして小学3年時から、レギュラーに選ばれる。周りは高学年の選手ばかり。
「そうなると父が、一層期待するんです。ある日、ファミリーレストランに行ったのですが、ステーキを食べていいのは私だけ。私の体を強くしようと思ったんでしょうね(笑)」。
父の思惑とは異なり、ステーキを食べた奥田は、「食」に目覚めるようになる。
「小学4年の時には初めて鮨屋に行ったんですが、この時、カウンターに座って食べた寿司の味は今でも忘れられません」。
中でも、イクラとウニが格別だったそうである。
中学生になった奥田は、父の期待通り、ソフトボールから野球に転じた。練習は段違いに厳しくなったが、奥田は、それにもめげる事なく、泥塗れになりながら白球を追い続けた。
「ところが、3年の夏かな。試合にあっさり負けてしまうんです」。
3年間、厳しい練習に耐えた事は自信になったが、チームプレーの難しさを知ったのもこの時である。
仲買人たちの話。
高校に進学した奥田は、野球からサッカーへ転向する。そういえば静岡はサッカーが盛んなエリアだ。奥田の進んだ高校は進学校だったが、スポーツにも力を入れていた。
「サッカー部に入部するんですが、経験が無いでしょ。流石に高校からでは、ハンディが多過ぎでした。それでも、何とかレベルを上げようと…」。
奥田は朝6時に登校し、ボールを蹴った。そうしているうちに、コーチが手伝ってくれる様になり、いつしか1年生全員が参加する様になる。
そんな中、監督から「マネージャーにならないか」と打診された。
「一度はお受けするんですが…」と奥田。皆についていこうと、1人で自主練習も重ねた。しかし、チームの他のメンバーのようにボールを支配する事はできなかった。
ただ、そのことより、マネージャーを打診されたことの方が、余程応えたのではないか。後にサッカー部を退部することにした。
これが、後々の転機の伏線となる。
「今まで、野球に打ち込んでいたでしょ。サッカーも、そう。でも、そういう打ち込むものが無くなってしまって…彷徨い始めます」。
退部すると、やることがなくなった。休みは一層長く感じられた。
夏休みを利用して仙台に向かったのは、そんな1年の夏である。
「母方の親戚がいる仙台に向かったんです」。
親戚が経営する海の家を手伝ったり、マグロの仲買をしている親戚もいたので、そちらを手伝ったりした。
その仲買の手伝いで生まれて初めて「男の社会を見た」と奥田。漁港に並べられたマグロ。磯の匂い。真っ黒に日焼けした男たち。筋肉は盛り上がり、マグロを観る目は厳しかった。目利きだけで生きている男達が、奥田を魅了する。
「元々団体競技には、苦い経験があったわけで。それで、一匹狼の様な仲買人達を見て、個人競技の様な仕事もあるんだと、そういう仕事を意識する様になったんです」。
静岡に帰ってみると、たまたま母の従妹が板前と結婚した事を知り、その店の手伝いをさせて貰った。板前という職人の仕事に興味を抱いたからだ。
「はっきりと飲食を意識したのは、あの時からだと思います。接客の楽しさも知り、何より板前という仕事に惹かれました」。
ここから、奥田の料理人生がスタートする。
料理人人生のスタート。
「どうせ修業するなら、厳しいお店で」と思ったそうだ。それが、18歳の奥田の選択。大学には進学せずに、静岡市内にあった割烹旅館「喜久屋」へ就職する。
住み込み。元々真面目な性格である。「とにかく、やってみた」そうだ。先輩からも、親方からも色々な事を学んだ。「今できないことは先送りにしないで、今やって克服した方がいい」と教えられた。
「あの頃は、とにかくハングリーでした」と奥田。接客を学ぶ為、市内のクラブでボーイの仕事も掛け持ちした。休みは殆ど無し。それでも、辛いとは思わなかった。ボーイの次には魚の卸売市場で仕事した。二足の草鞋。二倍の経験ができた。「魚市場は、学校のようだった」とも語っている。
頑張れたのは、二十歳で独立という目標を立てたから。
「いい店だね」、そう言われる居酒屋を作りたかったそうだ。
結局、「喜久屋」で5年勤務する。
この時代は奥田にとって、何を意味したのだろうか。「人の倍働き、人が10年かかる所を5年でできる事を実証したかった」と奥田。
「誰よりも頑張っていれば、いつか必ずいいことがあると信じ、むしろ辛い事や困難な事を好んでしていたかもしれない」とも。
「人ができないことをやってのける、その事に無上の喜びを覚えるタイプ」と自己評価もしている。
ともかく、この5年は、奥田の人生観というものを社会に問うという意味を持っていたのではないか。簡単にいえば「どこまでできるのか」を試す期間だったに違いないと思うのである。
少なくとも「京料理を体験しようと思った」のは、ある程度の自信が付いたからだろう。奥田は、静岡を離れ、京都に向かった。
「青柳」時代の話。
奥田の店は今、ミシュランから三つの星を獲得している。5年連続という快挙である。日本料理の名店の一つに数え上げられるのは、言うまでもない。
日本料理の精神を学んだのは、「喜久屋」の次に就職した京都の老舗料理店である。「この店で働いたのは半年に過ぎなかったのですが、日本料理が舌先だけのものではない事を痛感しました。掃除の仕方も学びました。ご主人から『400年経っていても磨けば光るんだよ』と教わりました、その一言は今も頭から離れません」。
建物だけではなく、床間の掛け軸、器からも、日本料理の精神が伝わってきた。「特に私は器と料理の関係性に興味を持ち、焼物にも惹かれていきます」。陶芸家の西岡小十氏の事を知ったのもこの時だった。
食材についても、勉強した。「特に野菜」と奥田。「京の料理人は、京野菜に対する思いが深いんです。静岡にいては思いもつかない様な方法で、野菜を利用していました」と言っている。
ところで、奥田の源流を語る時、よく語られる徳島の「青柳」に転職したのは、たまたま書店で手にした本がきっかけだと言う。無論、この「青柳」時代が、直接的な意味でも、間接的な意味でも、今の奥田の血肉となっているのは言うまでもない。
直接的な意味では、あの有名な小山裕久氏の下で修業できた事を指し、間接的な意味で言えば、奥田が生涯に亘っての親友であり、ライバルでもあると称する日本料理「龍吟」の山本征冶氏と出会い、共に腕を競い合う事ができた事を指す。
因みに、小山氏の下から3人のミシュランの星を獲得したシェフが誕生している。奥田も無論その1人だが、親友であり、ライバルだと言う山本氏も、「龍吟」にて星を獲得している。小山氏の名伯楽振りが伺える。
ともあれ、「青柳」時代である。料理人として、転職した奥田だったが、「青柳」で任されたのは、社長の運転手や下足番。「この時は根性を試されたと思っています」とのこと。その一方で、大切な気遣い方を学んだとも言っている。
この時、仕事振りが評価され、24歳で、「青柳そごう店」の支配人となっている。
初めて調理場に入った時の事も鮮明に記憶している。あの時の感激は一生忘れられない、とも。決してオーバーな表現ではない。視界がぱっと広がった、のではないか。その後も、何度も新鮮な驚きに出会った。小山氏に連れられ、パリの三つ星レストランに行った時も、そう。「フランス料理を食べ、感動し、衝撃を受けた」そうである。
「料理の世界にも、文化や芸術、或いは工業製品の様に世界基準があるのだと思いました」と語っている。
「青柳」での最後の1年間は、「青柳そごう店」の支配人兼料理長として働いた。
そして、その年の大晦日の夜。最後のおせち料理の盛り付けが、「青柳」時代の集大成とも言える仕事となった。
「銀座小十」、オープン。
奥田が銀座に、「銀座小十」を開いたのは2003年。銀座は、奥田にとっては、野球少年時代に追いかけた甲子園のようだった。ところで、この店名。どこかで、聞いた気はしないだろうか。そう、既に書いたが、陶芸家、西岡小十氏に由来した名前である。
「店をオープンする時に、先生からお名前を頂戴しました。店で使う器も、全部先生に焼いて頂きました。それが、先生の最後の作品ともなりました」。
西岡氏からは、「皆さんに好かれるお店にしなさいね」と言う言葉を掛けられたそうだ。その言葉は今も奥田の軸となっている。
業績の方はどうだったんだろう。「全然、お客様は入らなかったですね」と奥田は苦笑いする。「あまりに暇なので、仕入れた食材を料理して、自分で食べたりもしました。長い事、料理人をやっていましたが、初めての体験でした」。
お客が入らないまま、日々が過ぎる。資金が枯渇する。ついには家賃も、給料も支払いが困難になりかけたそうだ。「これが一番堪えた」と奥田。24時間、金の事で悩み、死ぬ事ばかり考えていたと言う。実際、奥田は目を閉じて自分は死ぬ運命なのかを考えた。だが、死んだ自分の姿は頭に出てこなかった。だから、どこかに何かチャンスがあるのではないかと思い、生きようと思い直した。
試練。
ある文豪の言葉に、「涙とともにパンを食したものでなければ…」と言うものがある。「…したものでなければ、人生の味はわからない」と続く。
まさにこの時の試練によって、奥田も又、一片のパンのありがたみを理解したのではないか。この時の経験がなければ、一つの料理も疎かにしない、今の奥田はなかったかもしれないと思うからだ。
苦境を潜り抜けた向こうに。
「もう、24時間、お金の事ばかりですよ。追い詰められていました。考える事と言えば…。でもね。ある時、冷静になって考えてみたんです。どうしてお客様がいらっしゃらないのだろうって」。
答えは、単純だった。知名度が無いからだった。「よし、もう一度だけ、頑張ってみよう」と、奥田自身のプロフィールや店の情報を載せた手紙を書き、出版社に送った。何らかの返事があれば、と。思い付いたアイデアにすがる様な思いだっただろう。幸い、ある出版社から連絡があった。
「東京カレンダーさんです。取材を受け、雑誌に大きく取り上げて頂きました」。
「銀座小十」を取り上げた東京カレンダーが発売された途端に火が付いた様に電話が鳴り出した。全て予約の電話である。
「見る見る内に予約帳が文字で埋まっていきました」。1本の電話が鳴る度に、有り難いと思った。嬉しさはお客にも伝わったはずだ。そうやって来て下さったお客を大事にしない訳はない。精魂を傾け、最高の料理をお出しした。次々にリピーターも増えていった。
雑誌に掲載された事で、火が付く事は少なくない。ただ、それを維持する事は難しい。「銀座小十」の様な名店となれば尚更だろう。期待外れでは、再訪はない。リピーターが次々増えていった事実にも、奥田の料理が認められたことが証明されている。
4年と4ヵ月の月日が流れた。「銀座小十」は知る人ぞ知る名店となった。予約の電話も、鳴り続ける。その時も、いつもの様に電話が鳴った。
星、獲得の話。
「正確な日にちは、2007年11月19日です。ミシュランガイド事務局の方からでした。その後、総責任者のジャン=リュック・ナレ氏からお電話を頂戴し、私共のお店がミシュランで三つ星を獲得したと伝えられたんです」。
もちろん、ミシュランの星の中でも三つ星は、一番獲得するのが困難である。試しにミシュランの基準を見てみると、「そのために旅行する価値がある卓越した料理」となっていた。無論、「パリの三つ星レストランで衝撃を受けた」奥田である。価値を十二分に理解していた。
「頭では理解できましたが、実感する事はできなかった」と奥田。まるで雲の上を歩いている様な気分だった。正式に「銀座小十」がミシュラン三つ星として表彰された時、約20年の人知れない苦労が、輝かしい栄誉へと昇華されたのだった。
思えば子供の頃から練習の鬼だった。自主練習にも明け暮れた。料理人を志しても、同じ。人知れず、練習を繰り返した。それが、実った。嬉しくない訳はない。
但し、奥田は次の様に語っている。
「私個人にではなく、お店に与えられた栄誉です。従業員、皆の勲章です。だから、『これからも気を引き締めて皆で頑張ろう』と従業員と話しました。その時、気付いたんです。あれだけ嫌いだった『チームプレー』をしていたのだと」。
今、奥田は、「日本料理を世界に広めたい」と公言する。
「私は、37歳で三つ星を獲得しました。神様は何を私にさせたかったのか、必死に考えました。『まだ十分に体力が残っている時に三つ星を獲得できたこと』の意味を考えたんです」。
「まだまだ体力がある訳ですから、何でもできる。和食だけにとどまらず、飲食全体の舞台を、もっと盛り上げる、それが私に課せられた使命だと。同時に、海外へ進出して日本料理を発信する事。それもまた私の使命だと思ったんです」。
話は変わるが、甲子園で優勝を果たした投手は、その後、「甲子園優勝投手」と呼ばれ、記憶に留められる。と、同時に重い十字架を背負わされる事になる。もっとも、どれだけの重みかは、本人にしか分からないものなのだが。
「三つ星」獲得。甲子園優勝とは別のことかもしれないが、これもまた同様の意味を持つのではないか。その3つの星の重さは、如何ほどのものなのだろうか。世界が奥田の「今」そして「未来」に注目している。
思い出のアルバム
| ツイート |
この企業・代表の方にコンタクトを取りたい方
この企業にご興味のある方、コンタクトを取りたい方、また代表にメッセージを送りたいといった方は、下記フォームよりご登録下さい。当社が連絡を取り、返信させていただきます(すべての取材先企業様、代表の方に連絡が取れるわけではありません。こちらから連絡がつく場合に限ります)。
例)テレビ番組用に取材したい、自社の商品をPRしたい、この企業で働いてみたい など
