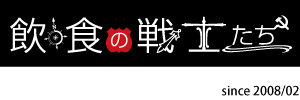


| 有限会社エイム 代表取締役社長 横内新一氏 | |
| 生年月日 | 1956年1月29日、東京都墨田区に生まれる。 |
| プロフィール | 3人兄弟の末っ子。小学4年から中学3年まで新聞配達を続け、その後もいくつかのアルバイトを体験。高校卒業後、京都、嵯峨野の和食料理店にて修業。八重洲の和食料理店をはじめ数店舗を経験した後、独立。1980年、「大衆割烹 新助」を開業。現在、「SAKABAR 新助」などを4店舗展開している。 |
| 主な業態 | 「新助」 |
| 企業HP | http://www.shinsuke.jp/ |
「3畳1間」のわが家。
今回、ご登場いただく有限会社エイム 代表取締役社長の横内新一が生まれたのは、1956年1月。1945年の終戦から11年しか経っておらず、戦後の爪あとがまだいたるところに残っていた。復興の足音が徐々に聞こえ出した頃でもあったのだろう。東京の墨田区。この界隈には、まだ長屋が軒を連ねていた。その長屋の一角に、横内の住まいがあった。3畳1間。5人家族の生活空間が、わずかそれだけだった。「父は会社員だったんですが、体が弱く、母もパートに出て家計を助けたんですが、それでも食べるのがやっとの生活でした」と横内は幼少時代を振り返る。そんななか3人兄弟は、貧しくも、文句を言わない健気な少年に育っていく。買い物担当は、末っ子の横内。真ん中の次男はご飯炊き。長男は、母親が勤めている会社でアルバイトをした。食べていくためには、子どもも働かなければならなかった。横内も、小学4年生から新聞配達を始めた。朝4時、寒い日も、嵐の日も、少年は家を出た。冬の4時といえばまだ闇のなか。どれほど少年の忍耐と勇気が試されたことだろう。「最初は月に2000円、中3になって辞める頃には8000円になっていました」と横内。当時の8000円は、いまでいえば7〜8万円だろうか。中3の時には、6〜7万円、つまり現在の6〜70万円の貯金があったというから驚いてしまう。だが、この貯蓄も、高校時代のストリートファイトで、相手に負傷を追わせた慰謝料としてすべて消えてしまうのだが。
「3畳1間」「共同トイレ」からの脱出。
横内が、中学2年の時、横内家は6畳のアパートに引っ越した。子どもたちの体も大きくなっていたため、長男は、仕事先で寝泊りした。横内は新聞配達とバレー部に所属。部活動に専念した。授業は貴重な睡眠時間だった。ところで、中学で横内はバレーを辞めるのだが、高校になって授業で行なわれたバレーの試合を観た当時のバレー部監督が目を留め、1年間限定という約束でバレー部に入り部長を務めたという。運動神経も群を抜いていたのだろう。ケンカも強かった。だが、ケンカよりも、授業よりも、クラブ活動よりも、一番は仕事だった。働かないと「小遣い」さえなかったからだ。高校時代もさまざまなバイトを経験。高校3年生の頃には20人程度が入れる小さなラーメン店だが、店長のような仕事を任されている。幼少の頃から「独立起業」をめざしていたが、この頃になると、その思いが鮮明な具体像を持つようになる。料理人も、その一つの姿だ。地元の店で就職したが、2ヵ月後、京都、嵯峨野の和食料理店で働き口が見つかり、退職。この料理店で2年間修行している。18歳から20歳。当時の横内と同年代の青年がいまや横内の店にも入店してくる。学生アルバイトも少なくない。「当時と現在ではハングリー精神も違うのでしょうが、独立を希望するなら、若い時代の数年間を無駄にしてほしくないと思います」と横内は、厳しくも温かい目で青年たちをみつめる。それは当時の自分と、いまの若者たちを重ねるからかも知れない。大事にするのは、彼らの思いの強さだ。さて、京都から2年後、東京に戻った横内は、八重洲や目黒の店で仕事を覚えた。友人の一人が神楽坂で店を構えたのは横内が23歳のときだった。
嬉しい反面、悔しくて、泣いた。
昔からの友人だった。悪いことも一緒にした。店を持ちたいな、と語り合ったこともあった。そんな友人が、神楽坂で小さな、けれど横内には羨ましくてしかたのない「自分の店」を開いた。当時、横内は目黒で働いていたが、その店が終わると神楽坂に出かけ、この友人の店を手伝った。「嬉しかったですね。友だちですから。でも、アパートに帰って一人になると、悔しくて涙がとまらないんです」。「友人の場合、家に余裕があったから」、横内は小さくつぶやいた。悔しさの、理由の一つはそれだった。どうしようもない、家庭環境。だが、縛られ続けては駄目だ。横内はこのとき1年後の開業を絶対の目標に据えた。料亭に入り、見習いから再び修行を開始し、1年後、24歳になった年の4月29日に「大衆割烹 新助」を出店した。この年に横内は結婚もしている。当初から売上は好調。悔し涙から、1年、喜びに包まれた。「売上が良かったこともあって、妻と2人。2DKの部屋を借り、風呂もトイレもある家で初めて暮らしました。ただ、両親がまだ共同トイレの家に住んでいましたから申し訳ないな、と。それがあって、1年目、予想以上に売上が伸びてもテングにならずにすんだのだと思います」。ところで、この1号店から2号店の出店までに7年の間がある。「最初の3年間は、好調でした。でも、4年目に入ると徐々に常連さんが減っていくんです。私もうまく行き過ぎて、さすがにテングになってしまっていたのかも知れません」と横内。だが、家族が食べるだけの収入はあった。「1号店が辺鄙なところだったので、駅前に出たいなとは思っていました」。店舗数を増やすという目標はなかったが、「駅前の人通りの多いところで勝負してみたい」という気持ちは強かった。これが2号店の出店につながる。
有限会社エイムの基盤ができるまで。
1日のサイクルはこんな感じだ。AM2:00。「大衆割烹 新助」の仕事が終わったその足で、2号店の「ゴリラ亭」に向かう。ここで翌日のカレーの仕込みをする。2号店は、アルバイトだけでも回るようにカレーショップにしたが、味を決める仕込だけでは自ら行なった。AM9:00から、今度は「新助」のほうの仕込み。12:00〜ランチをやり、PM17:00頃から「新助」が本番の時間を迎える。1日をぐるりとひと回り。仕事以外にほとんど空いている時間もない。「人生のなかで一番、働いた」と横内。だが、売上のほうは横内が必死で働くにもかかわらず、低迷した。「絶対、いける」と満を持して出店しただけに、引き下がることもできない。ここで横内は、人の育成を実践する。「アルバイトの子を社員に昇格させたんです。すると、がんばってくれるようになって。2年目の頃には、小さな店ですが、10万〜12万円はコンスタントに上がるようになっていました」。この「ゴリラ亭」も、「新助」も、横内一人がひっぱってきたような店だった。だが、この時から徐々に、若手が店の顔になり始め、彼らが店をひっぱるという機運も生まれだしたのではないだろうか。そういう機運も熟した1993年に出店した3号店が、初月から「バカあたり」した。京葉線新浦安駅ビル「アトレ」に出店した「味の居酒屋 新助」である。43坪。広さも申し分なかった。1号店ではなかなか取り込めなかった新規顧客が、つぎつぎ訪れ、回転した。売上も、利益も立ち、有限会社エイムの基盤が出来上がる。1995年には、関連会社として株式会社「一兆」を設立している。以来、数十年、1980年の開業からは、2010年6月現在で30年を数える。「SAKABAR 新助」などブランドも増え、店舗数は4店舗に広がった。いずれの店も、人気が高い。その理由を「大手の居酒屋ではできない、店舗ごとで行なう新鮮な料理」と横内はいう。価格でも負けない。実際、年数回、実施するモニターでも「味、価格」ではつねに高い評価を獲得している。だが、サービス面の数字がいささか落ちる。この改善がいまの課題といえば課題だ。
料理をつくること、食べること、が好き。
そんなサービス面を強化するのは、これからの若手のスタッフたち。互いに切磋琢磨する環境作りにも横内は目を向けている。求める人物像は「料理が好き、食べることが好き」、これが基本だという。学歴や、たとえば大学名で採用するようなことはしない。福利厚生面ではまだまだ未整備のところはあるが、逆に、横内の会社だからできる「配慮」を実施している。スタッフの定着率がいいのは、その横内の思いが伝わるからだろう。大手ではなかなか学べないことが、「学べる環境」でもある。人を育てるという意味では、企業の規模も、ちょうどいい。社長と接する機会が多いのも、成長意欲の高い人にはうってつけといえるだろう。「当時は、多くの人が貧しかった」、幼少時代を振り返ってもらった時に、横内はそういう風に、1950年後半〜60年前半を語った。当時からみれば「食」に対する社会の意識もずいぶんかわったことだろう。横内家の食卓に並んだのは、どんな料理だったのだろうか。失礼を省みずいえば、味わうためではなく、空腹を満たすための「料理」だったかも知れない。だが、その料理が、一人の料理人を、経営者を育てたことも事実である。このハングリー精神を持った経営者だから「強い人」を育てられる、これもまた事実なのである。
 |
 |
 |
この企業・代表の方にコンタクトを取りたい方
この企業にご興味のある方、コンタクトを取りたい方、また代表にメッセージを送りたいといった方は、下記フォームよりご登録下さい。当社が連絡を取り、返信させていただきます。
例)テレビ番組用に取材したい、自社の商品をPRしたい、この企業で働いてみたい、中学時代の同級生だった など
